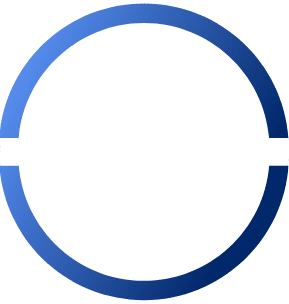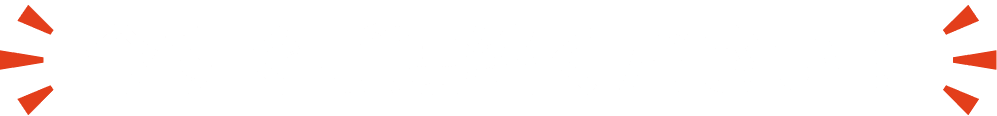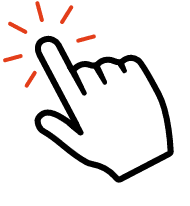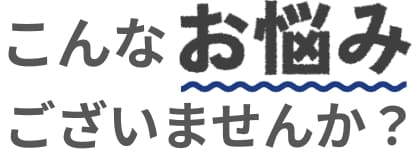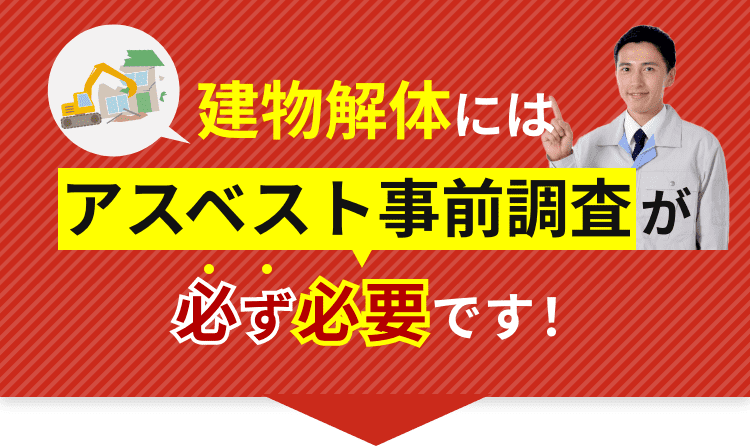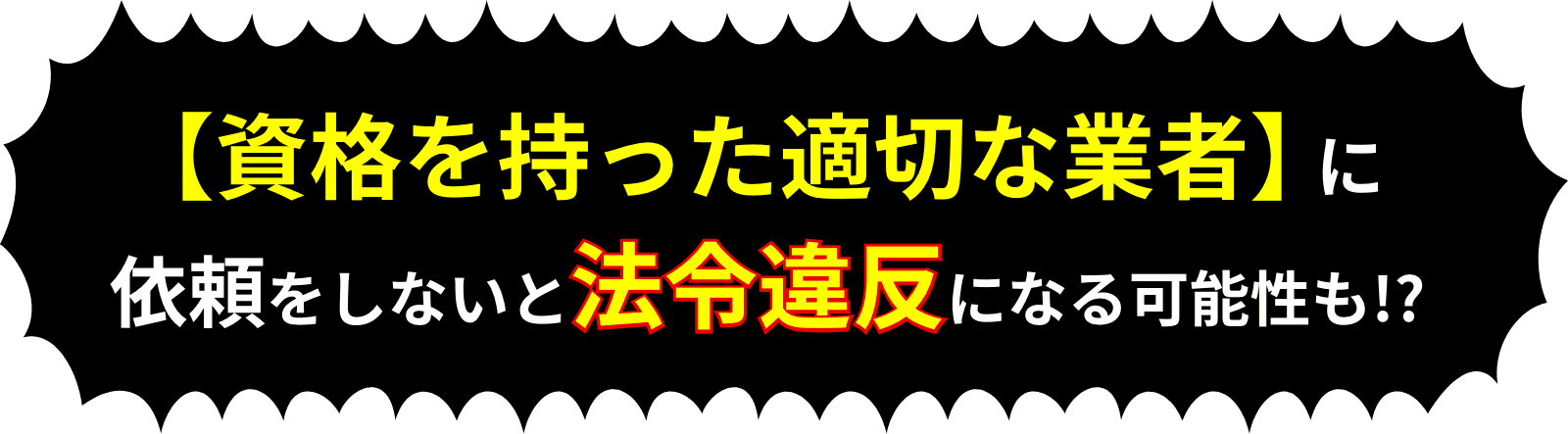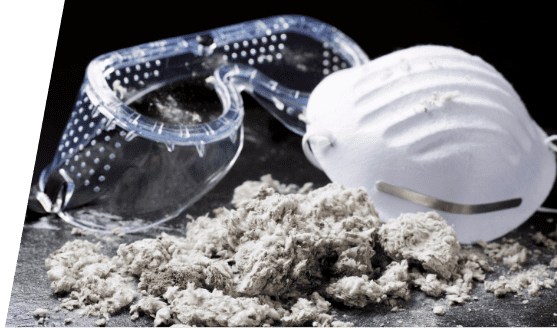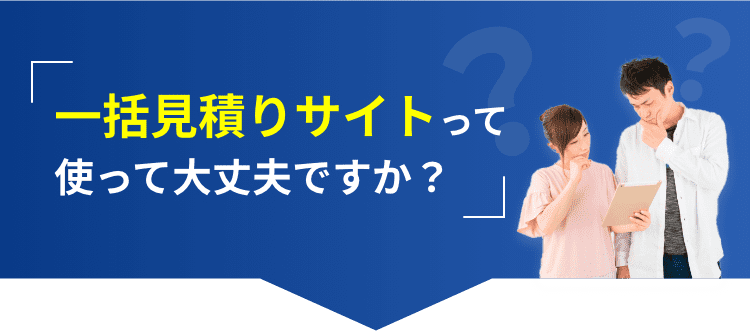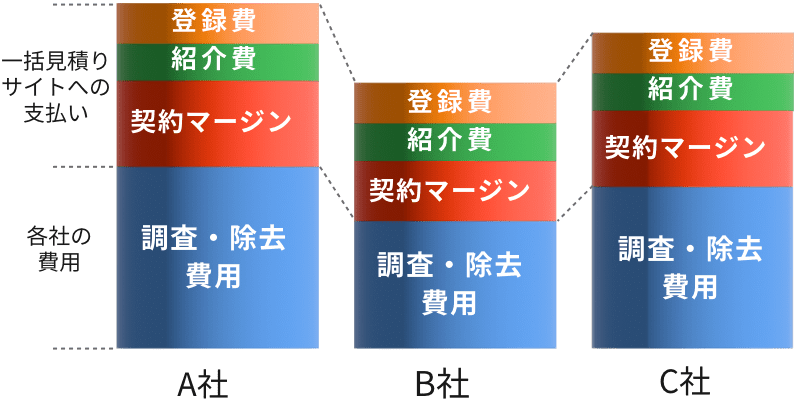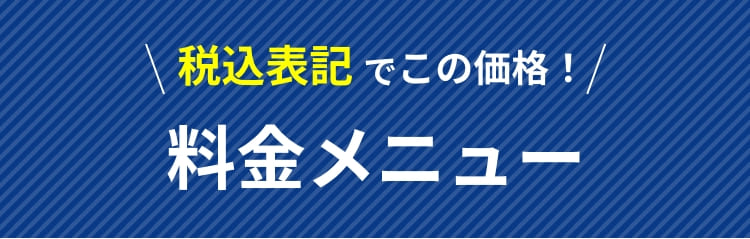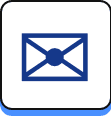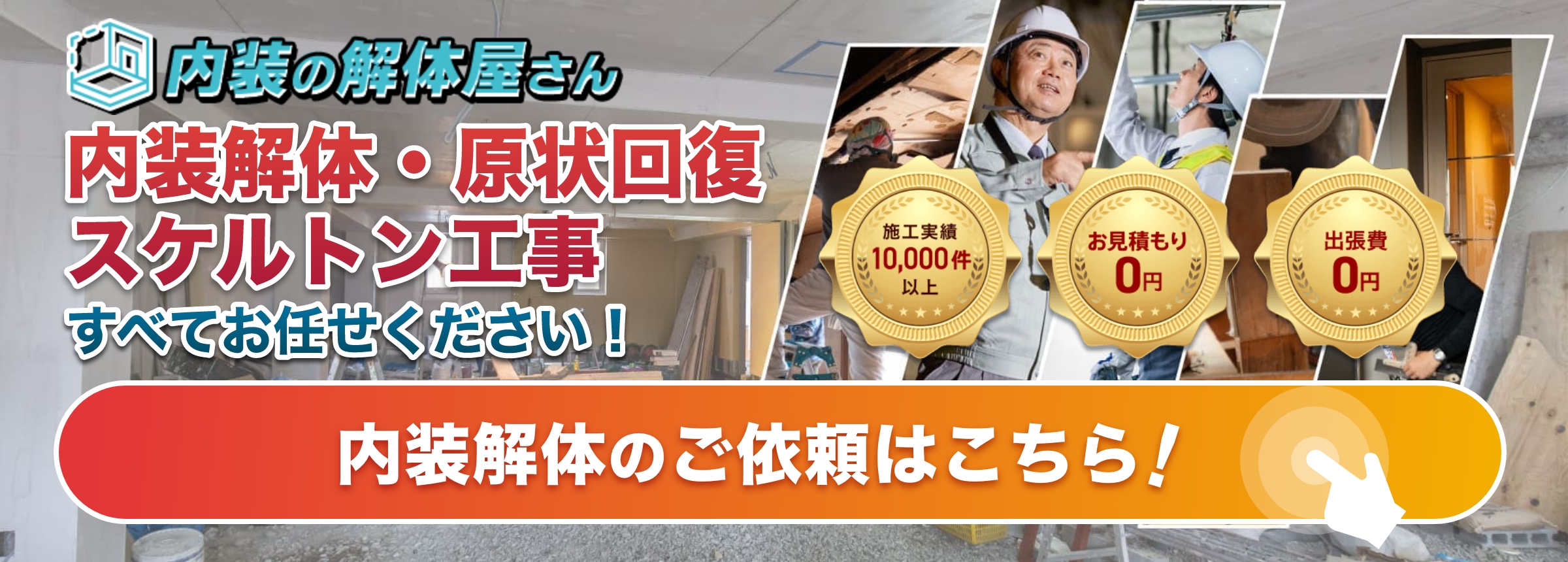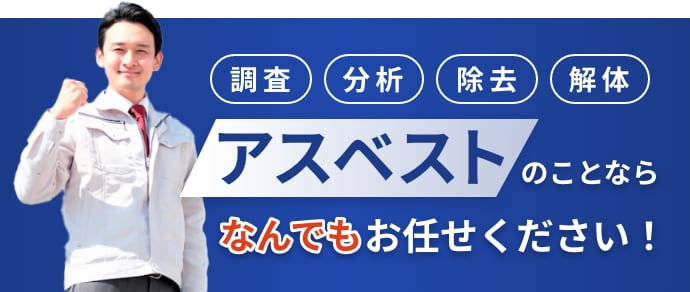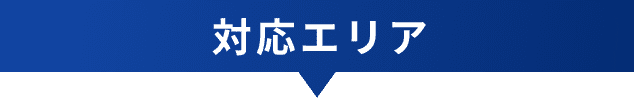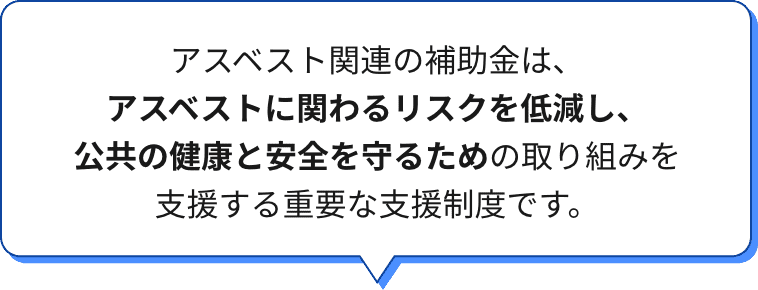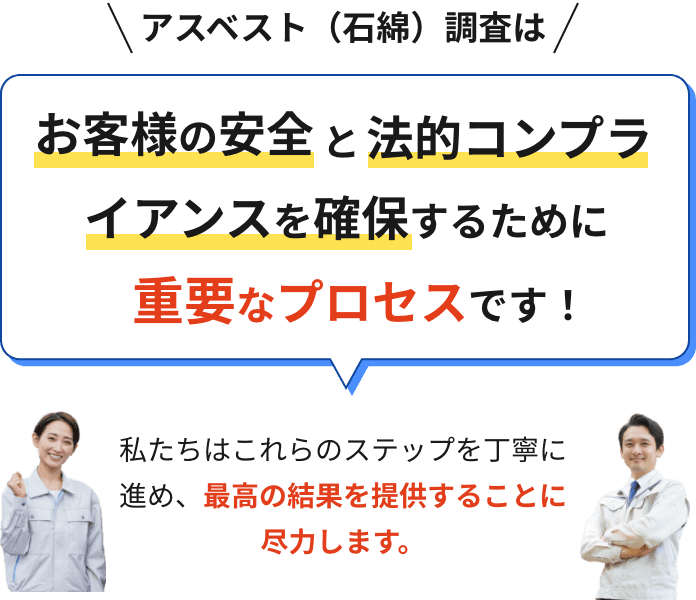アスベスト(石綿)が使用されている箇所としては、【耐火建築物の梁や柱】【エレベーター周辺】【ビルの機械室やボイラー室の天井や壁】【立体駐車場や体育館の天井や壁など】が挙げられます。これらは主にレベル1の危険度に該当し、耐火性や断熱・吸音性を求められる場所で使用されることが多いです。
特に昭和30年代から50年初頭までの建築物には、アスベストが使用されている可能性が高いです。しかし、一般的な住宅の建材としては、レベル1のアスベストはほとんど利用されていません。
レベル1のアスベストを取り扱う際には、解体工事をそのまま行うとアスベストが大量に飛散する危険性があるため、まずはアスベストの撤去作業が必要となります。また、解体を伴わない改修の場合には、飛散を防ぐために薬液を使用した「封じ込め工法」や、板状の材料で密閉する「囲い込み工法」が適用されます。
2番目に危険性が高いレベル2には、石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などが分類されます。これらは密度が低いため、崩れると粉じんが広がる可能性があります。
アスベスト(石綿)が使用されている箇所としては、【ボイラーの本体や配管、空調ダクトの保温材】【建築物の柱や梁、壁の耐火被覆材】【屋根用の折板裏の断熱材】【煙突の断熱材】が挙げられます。レベル1と同じく、アスベストが飛散する危険性があるため、専門的な除去作業が求められます。
また、改修作業など解体を伴わない場合でも、アスベストの飛散を防ぐために「封じ込め工法」や「囲い込み工法」を用いることが可能です。封じ込め工法では、薬液を使ってアスベストを固定し、飛散を防ぎます。囲い込み工法では、板状の材料でアスベストを覆い、密閉します。
最も危険性が低いレベル3には、アスベストを含む建材が含まれます。アスベスト含有建材は内部にアスベストが含まれているため、飛散リスクは低いですが、破損などにより内部からアスベストが飛散する可能性があるため注意が必要です。
アスベストの危険度レベル3は、主に【建築物の屋根材】や【外壁材、内装材の天井・壁・床】【ビニール床のタイル】などに使用されています。
建築物の解体や改造、補修などの建設工事を行う際には、アスベストが含まれているかどうかの事前調査が必要となります。特に、特定の条件を満たす解体作業を行う場合には、調査結果の届出が必須となります。2020年までは、レベル1・レベル2の建材にアスベストが含有されていた場合のみ、都道府県庁への調査結果の届け出が義務化されていました。しかし、レベル3のアスベスト建材が含有されていた場合には報告の義務付けがありませんでした。
しかし、2022年4月1日からは、一定以上の規模の建築物等については、アスベスト含有建材の有無にかかわらず事前調査の結果を都道府県へ報告することが法律で義務付けられています。これは大きな変更点と言えます。
作業時には注意喚起の案内や湿潤化が必要ですが、レベル1・2に比べれば前室の設置のような厳重な対策は不要で、作業員のばく露対策は簡易的になります。ただし、レベル3といってもアスベストであることには変わりなく、飛散は起こるため慎重に作業を行わなければ健康に害を及ぼす危険性は十分にあります。












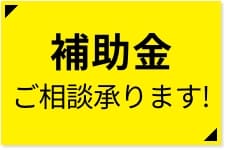




 TOPページ
TOPページ